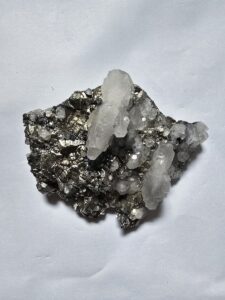西川紀代子
はじめに:老いを照らす一句の光
「健やかに物忘れして敬老の日」。西川紀代子氏によって詠まれたこの一句は、私たちの心に温かく、そしてどこか軽やかな風を吹き込んでくれます。
一般的に「物忘れ」という言葉には、認知機能の低下や老いの寂しさといった、やや否定的な響きが伴いがちです。しかし、作者はあえてその前に「健やかに」という言葉を置きました。
この大胆で優しい肯定の眼差しは、私たちが抱く「老い」のイメージを根底から揺さぶり、より豊かで自由な生き方への扉を開いてくれるかのようです。
情報が洪水のように押し寄せ、効率性や生産性が絶えず求められる現代社会。
その中で私たちは、知らず知らずのうちに「忘れること」への恐怖を植え付けられているのかもしれません。しかし、この句は、忘れることは決して衰えや敗北ではなく、むしろ健やかに生きるための自然な営みであり、一種の智慧でさえあると、穏やかに語りかけてきます。
本稿では、この味わい深い俳句を羅針盤として、「健やかな物忘れ」という視点から、これからの時代を生きる私たち、特に高齢期を迎えた方々が、より心豊かに日々を過ごすためのヒントを探ってみたいと思います。
執着からの解放:「物忘れ」がもたらす精神的な自由
人間は記憶と共に生きています。
楽しかった思い出は人生を彩り、苦しかった経験は未来への教訓となります。
しかし、記憶は時に、私たちを過去に縛り付ける重い足枷ともなり得ます。
かつての成功体験への執着、人間関係の中で受けた心の傷、満たされなかった願望への悔恨。そうした記憶は、何度も心の中で反芻され、現在の自分を不自由にします。
この句が示す「健やかな物忘れ」とは、こうした過去のしがらみや心の澱(おり)を、少しずつ手放していくプロセスと捉えることができます。
それは、大切な思い出までをも消し去るという意味ではありません。
むしろ、自分を苦しめる不要な記憶という荷物を降ろし、心を軽くすることで、「今、この瞬間」をより鮮やかに生きるための精神的な余白を取り戻す作業です。
仏教の教えにも通じるものがありますが、苦しみの多くは執着から生まれると言われます。
物忘れは、意図せずして私たちをその執着から解放してくれる、自然からの贈り物なのかもしれません。
忘れることで、私たちは人を赦(ゆる)し、過去の失敗を受け入れ、新たな気持ちで今日という一日を始めることができるのです。
それは、記憶力の低下という現象を、精神的な成熟と自己再生の機会として捉え直す、非常に創造的な生き方と言えるでしょう。
「健やかさ」の本質:変化を受け入れる心のしなやかさ
この句の核心は、やはり「健やかに」という一語にあります。
では、ここで言う「健やかさ」とは、具体的にどのような心の状態を指すのでしょうか。
それは単に病気ではないという身体的な健康だけを意味するものではないはずです。
むしろ、変化していく自分をあるがままに受け入れ、ユーモアさえもって向き合う、精神的なしなやかさや強靭さ(レジリエンス)を指しているのではないでしょうか。
年齢を重ねれば、誰もが若い頃と同じではいられません。
身体には変化が現れ、記憶力や集中力にも影響が出るのは自然なことです。
「昨日食べたものが思い出せない」「人の名前がすぐに出てこない」。
そんな自分に直面した時、過度に落ち込んだり、焦ったりするのではなく、「まあ、いいか」と笑って受け流せる心の余裕。それこそが、健やかさの源泉です。
この句には、そんな朗らかで愛すべきお年寄りの姿が目に浮かぶようです。
物忘れさえも人生のスパイスとして楽しみ、深刻になりすぎない。
その軽やかさは、周囲の人々の心をも和ませ、温かい人間関係を育む土壌となります。
完璧ではない自分、老いていく自分を否定するのではなく、丸ごと愛おしむ自己受容の精神。それこそが、何物にも代えがたい「心の健やかさ」であり、この句が私たちに伝えようとしている最も大切なメッセージなのかもしれません。
### 敬老の日:社会との繋がりの中で生きる
最後に、「敬老の日」という季語が持つ意味にも思いを馳せてみましょう。
この言葉があることで、この句は単なる個人の内面的な心境を詠んだものに留まらず、社会との関わりの中で生きる高齢者の姿を映し出す、より広い視野を獲得しています。
敬老の日は、長年にわたり社会に貢献してきた高齢者を敬い、その長寿を祝う日です。
しかし、祝われる側である高齢者自身が、老いを悲観し、内に閉じこもっていては、その日はどこか寂しいものになってしまうでしょう。
この句のように「健やかに物忘れして」と、明るく開かれた心でいることで、初めて家族や地域社会との間に、温かい心の交流が生まれるのではないでしょうか。
過去の肩書きや役割といった鎧を脱ぎ捨て、一人の人間として、今のありのままの自分で他者と向き合う。
物忘れは、時としてそうした新しい関係性を築くきっかけを与えてくれます。
「昔はこうだった」という話ばかりではなく、今日の天気や庭に咲いた花について語り合う。そんな何気ない日常のやり取りの中にこそ、人生の喜びは満ちています。
「健やかな物忘れ」は、高齢者を孤立から守り、再び社会へと繋ぎ止める、見えない絆の役割を果たしているのかもしれません。
結論:豊かに老いるための智慧として
西川紀代子氏の「健やかに物忘れして敬老の日」という俳句は、老いという人生の自然なプロセスに対する、深く、温かい洞察に満ちています。
この句が教えてくれるのは、物忘れは嘆き悲しむべき衰えではなく、過去の重荷から自らを解放し、「今」をより良く生きるための、天から与えられた智慧であるということです。
それは、変化していく自分を否定せず、ユーモアをもって受け入れる「心のしなやかさ」。
不要な記憶や執着を手放し、精神的な自由を謳歌する「軽やかさ」。
そして、ありのままの自分で社会と関わり、温かい人間関係を育む「開かれた心」。
これからの超高齢社会において、私たちは皆、いずれ老いと向き合うことになります。
その時、この一句は、私たちの足元を照らす確かな灯火となるでしょう。記憶の確かさや若さに固執するのではなく、忘れることを恐れず、日々の小さな喜びを大切に生きる。
そんな「健やかな物忘れ」の精神こそが、人生100年時代を心豊かに、そして朗らかに生き抜くための、最も大切な鍵となるに違いありません。