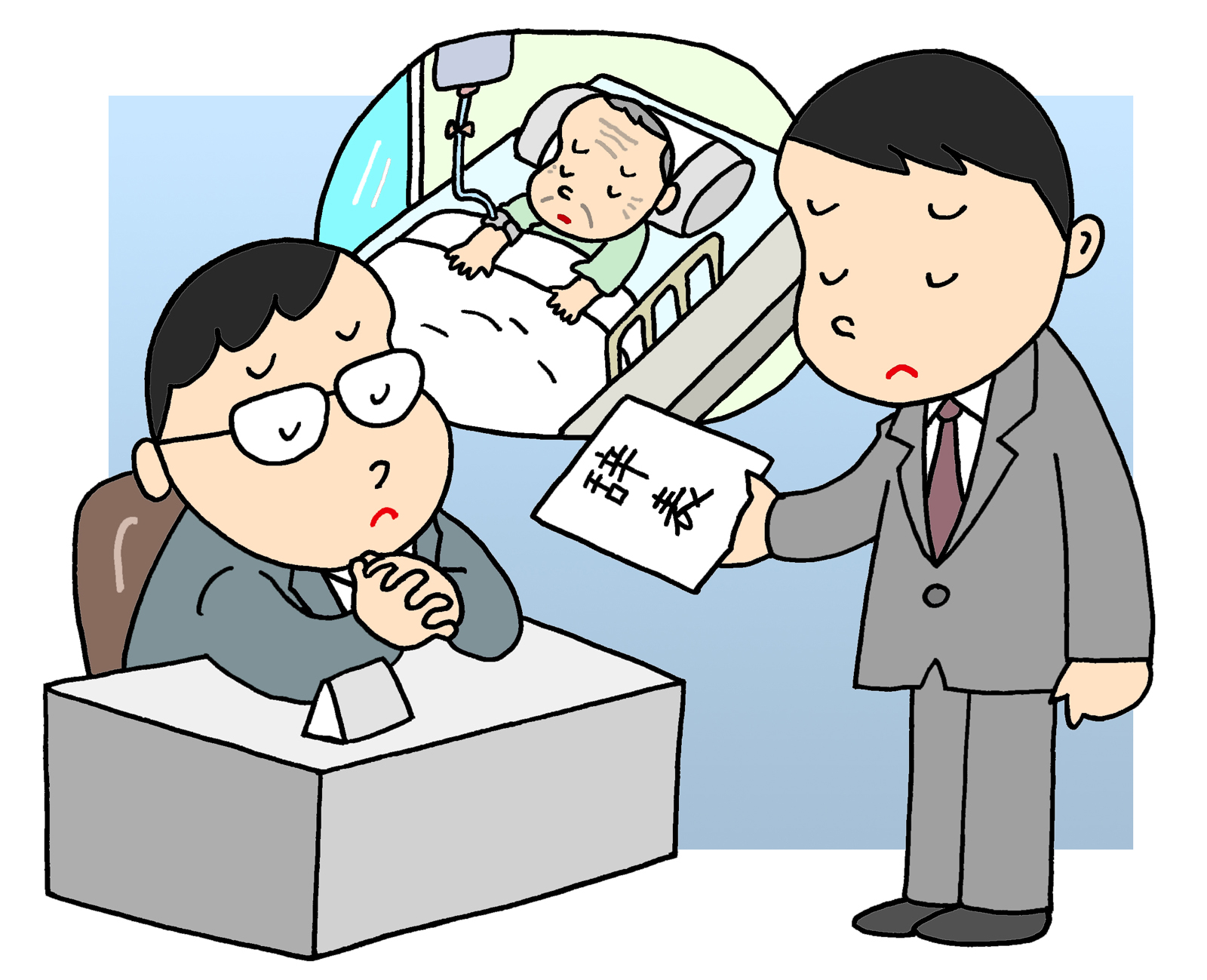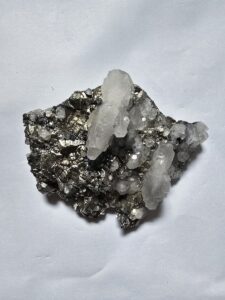今回は「介護離職」という、どこか遠い話のようでいて、私たち福祉施設の職員自身や、私たちが支えるご家族にも深く関わる課題について、お話ししたいと思います。
年間10万人が仕事を辞めている現実
皆さんはご存じでしたか?日本では、親や配偶者の介護を理由に、年間約10万6,000人もの方が仕事を辞めています(2022年統計)。この数字には、私たちのように福祉現場で働いている人たちも含まれているかもしれません。
特に50代後半の「働き盛り」世代が多く、これから親の介護が本格化していく中で、「自分もいずれ…」と感じている方もいるのではないでしょうか。
なぜ、そんなにも離職してしまうのか?
理由のひとつは、日本の文化的な価値観です。「親の面倒は子どもが見るもの」という儒教的な考え方が、今もなお根強く残っています。それに加えて、刑法218条には「保護責任者遺棄罪」があり、要介護者を放置すれば罪に問われる可能性もあります。
つまり、日本では「道徳」と「法」の両面から、家族に介護の責任が重くのしかかっているのです。その結果、働きながら介護を担う「ビジネスケアラー」は心身ともに疲弊し、やむを得ず仕事を辞めるという選択をせざるを得なくなっているのです。
2025年問題と介護の未来
さらに、私たちにとって見逃せないのが、「団塊の世代」が2025年に全員75歳以上になるという事実です。この世代の多くが要介護状態に入ることが予想されており、それを支えるのは私たち40~50代。つまり、これからが本番なのです。
介護離職が個人や家庭の問題にとどまらず、企業の戦力低下、ひいては日本経済への損失(2030年には年9兆円規模)という形で広がっていくことが、すでに国の試算で明らかになっています。
休業制度はある。でも、使われていない
介護休業や介護休暇といった制度は整備されています。最長93日の介護休業や、1時間単位で取得できる介護休暇、時短勤務や深夜業免除も可能です。
しかし、実際に制度を利用している人はほんのわずか。介護休業の取得率はわずか1.4%(2022年)。そもそも制度の存在を知らない、または「周囲に迷惑をかけたくない」と気兼ねして使えない――そんな声が多く聞かれます。
だからこそ、私たち施設職員がまず知っておくこと、伝えることが大切なのです。
スウェーデンに学ぶ:介護は「自由意思」
ところで、介護離職がほとんど存在しない国があるのをご存じでしょうか?それが、北欧の福祉先進国・スウェーデンです。
スウェーデンでは、「親の介護は子どもの自由意思」という文化が定着しており、法的にも介護は市町村の責任と明記されています。介護サービスは自宅でも施設でも手厚く、公的支援が充実しているため、家族が退職してまで介護に入る必要はありません。
驚くべきことに、スウェーデンの高齢者は「子どもに世話してもらおう」とすら思っていません。むしろ、「できることは自分でやりたい」「足りない部分は社会に頼る」という自立の精神が強いのです。
私たちにできること
私たち福祉職も、例外ではありません。施設職員として、ご利用者の家族が介護負担に悩んでいる姿を見かけることもあるでしょう。そのとき、「介護休業、知っていますか?」「地域包括に相談してみては?」と声をかけることで、ひとつの介護離職を防げるかもしれません。
また、自分自身や同僚が将来的に介護を担う立場になることもあります。そうなったときのために、情報を知っておくこと、自分自身の働き方を見直すこと、必要なら声をあげることも重要です。
介護は個人だけで背負うものではありません。
社会全体で支える仕組みと、文化的な価値観の転換が、これからの日本に求められています。
施設職員である私たちが、まずその一歩を踏み出す存在になりませんか?